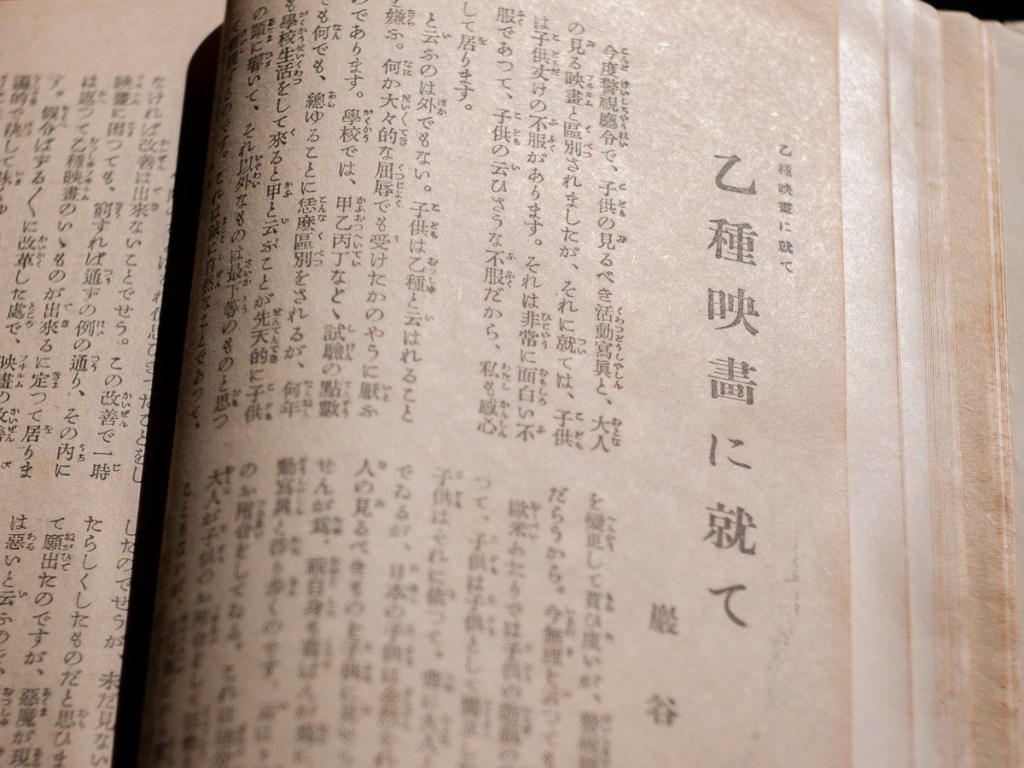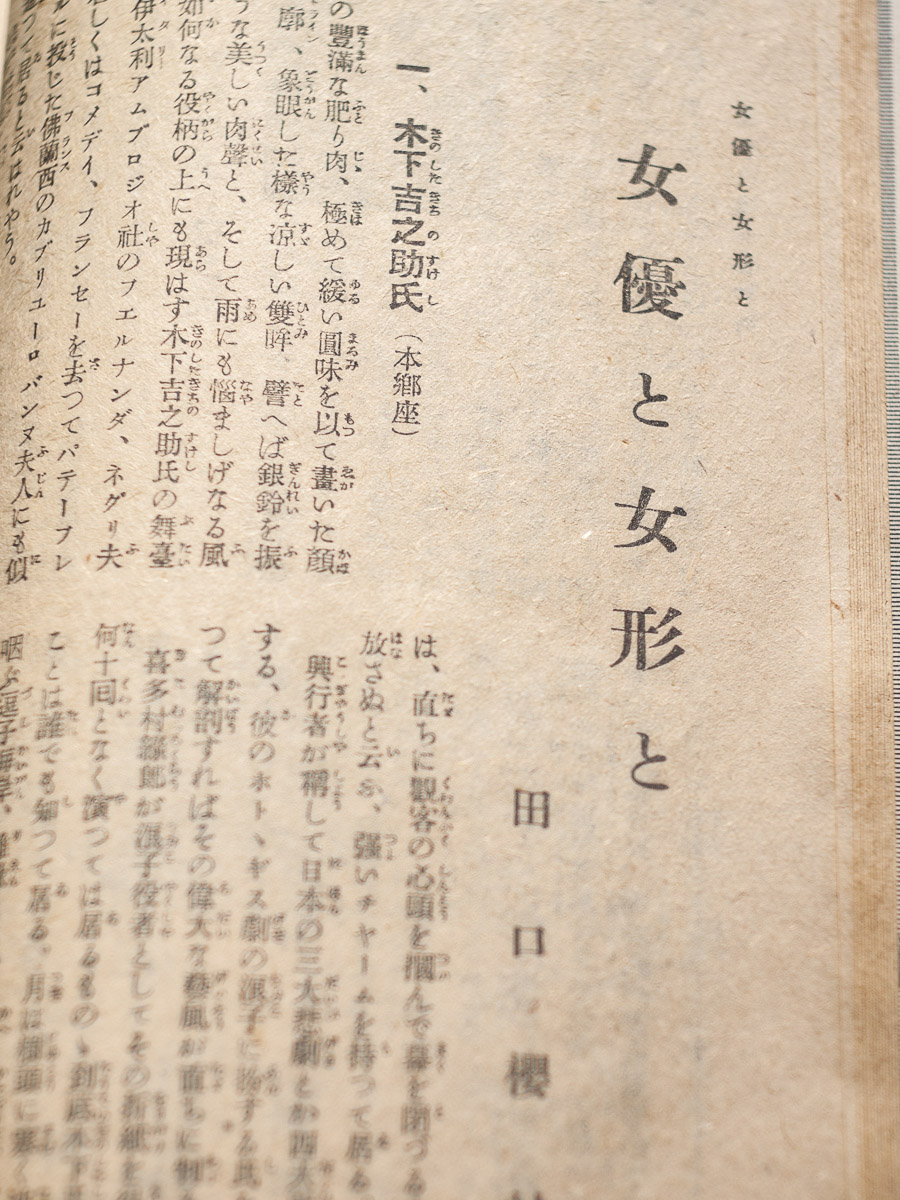情報館・雑誌(和書) より
『活動畫報』誌は飛行社から出されていた前期(1917年1月号〜1919年4月号)と、正光社から発行されていた後期(1919年5月号~1923年)に分かれており、後期の途中で菊判(21.8×15.2センチ)から四六倍判(25.4×18.8センチ)に変更されています。今回入手した1917年(大正6年)10月号は前期の一冊でその中でも初期に公刊されたもの。





表紙はビリー・バーク。
巻頭カラーグラビアにドロシー・フィリップスを配し、単色グラビアにはマーガレット・スノウ、コンスタンス・タルマッジ、シドニー・チャップリン、ヘレン・ギブソン等のハリウッド俳優、吾妻孟夫、木下百合子等の邦画俳優が登場していました。







新作では旧劇『朝比奈三郎』(天活東京、澤村四郎五郎主演)と『白露草子』(小林商会、市川海老十郎主演)二作が見開きで大きく扱われています。他にビリー・バーク主演の連続劇『グロリア物語』、ベルティーニ主演の『オデット』、マーガレット・スノウ&フローレンス・ラバディ主演の『美人郷』、日活京都派の旧劇『白虎隊』、日活東京派の新派劇『戀の一念』等が紹介されていました。
この雑誌が発行される約2か月前、1917年7月の終わりに活動写真取締規則が施行され検閲が強化されました。映画製作、観賞にどのような影響が及ぶのか当時の愛好家にとっても大きな関心事だったようで、本誌でも「乙種映畫に就て」「活動寫眞に就て」「不合格となつた乙種映畫」「活動寫眞檢閲場を觀る」の4つの記事で現場の実態を紹介しています。
また国外映画人の紹介欄では俳優4名(ブランシュ・スウィート、ヘンリー・オルサール、マリー・ドレスラー、ビリー・バーク)とヘレン・ホームズの夫で(以前に紹介した9.5ミリ版『ヘレン・ホームズの花嫁争奪戦』を監督した)J.P.マクゴワンが紹介されていました。
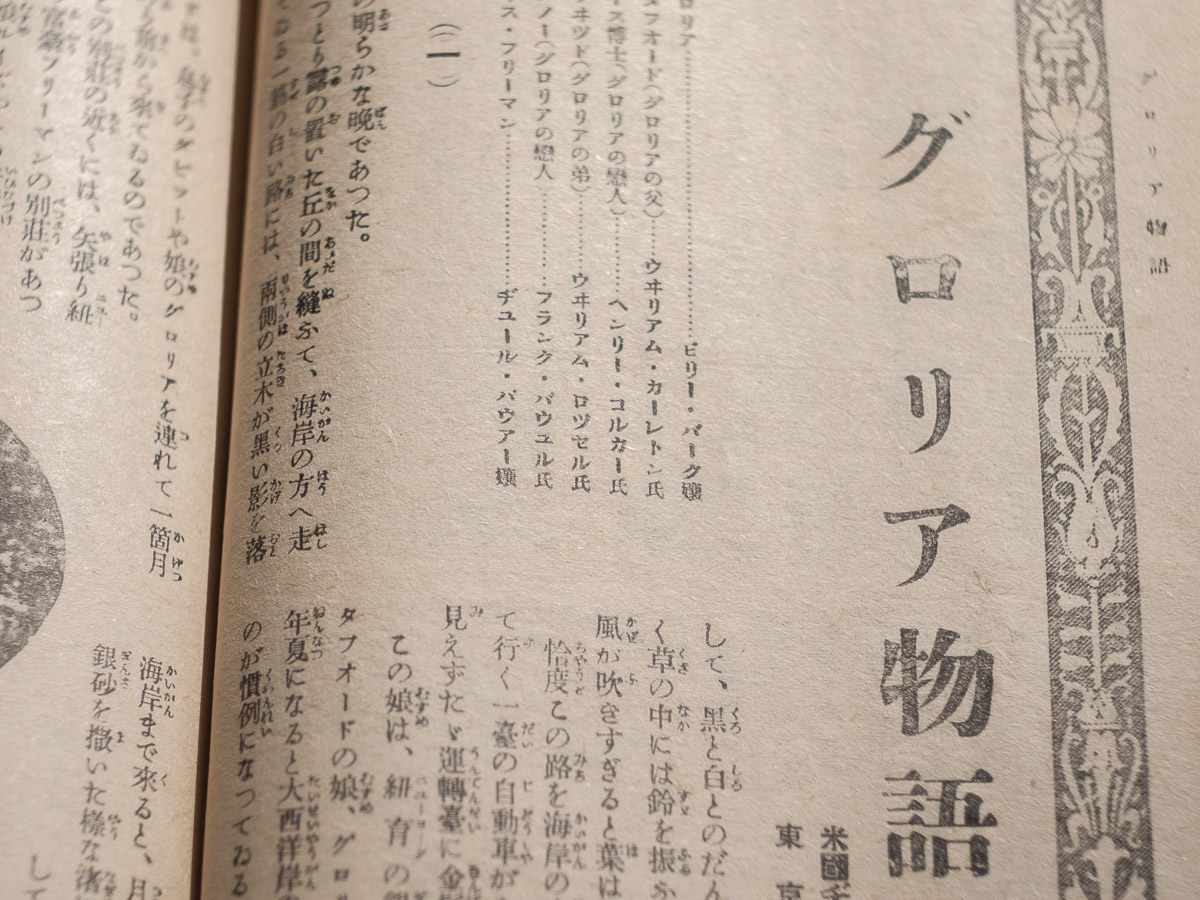

読み物としては『グロリア物語』を筆頭に『戀の一念』『朝比奈三郎』『白虎隊』と続き、フェアバンクス主演作『快男児』とネヴァ・ガーバー主演の連続活劇『電話の聲』も収められています。


また雑誌後半には邦画俳優からの寄稿が二つ(澤村四郎五郎が現場の苦労を綴った「日暮里撮影所にて」、木下百合子が関西旅行時の雑感を述べた「諏訪町より」)が含まれていました。四郎五郎の文章は作品から受けるイメージと違い内向きな穏やかさがあって面白かったです。
菊版型當時は、「活動寫眞雑誌」式な娯樂向き一方に編輯してゐたが、四六倍版になると共に、此の雑誌の編輯内容はガラリ變つて可成り高踏的なものとなつた。
「映畫ジャーナリズム盛衰秘史(6):活動畫報(續き)」 木挽町人
キネマ週報 1930年10月3日付第32号
「映畫ジャーナリズム盛衰秘史」で木挽町人氏は通俗娯楽路線と趣味研究高尚路線の二つを区別しています。活動写真雑誌と前期・活動画報が前者に当たり、後期・活動画報と活動倶楽部が後者に当たるとのこと。ただ、正直この区分がピンとこないんですよね。
今回紹介している『活動畫報』 大正6年10月号や以前に紹介した大正7年1月号などをみると、グラビア写真と読み物(映画の粗筋を読み物化した文章)が多く論考の比重が少ないのは事実です。また論考の寄稿者に名の知られたメンバーがおらず、個々の作品や映画界の諸傾向を深堀りはしていないとは言えます。
とはいえ大正7年1月号ではグラビア・作品紹介・俳優紹介・読み物の全てに『レ・ヴァンピール』と『亂菊の舞』が取り上げられていました。表紙、目次には言及されていませんが実質的に「小特集:ルイ・フイヤード監督作『レ・ヴァンピール』&ナピエルコウスカ主演『亂菊の舞』」が組まれていることになります。後期活動画報と活動倶楽部が得意としていたポエム風のレトリックを排し、必要最低限の情報を伝えて「後は自分で見て判断してね」と読み手に投げる編集方針だったと見て取れるのです。
大正6年10月号にも同じことが言えます。
当時の映画界で大きな問題となっていた「検閲」については、論考二つ(「乙種映畫に就て」「活動寫眞に就て」)で一般論を語り、もう二つの記事(「不合格となつた乙種映畫」「活動寫眞檢閲場を觀る」)で具体例を挙げていきます。
また、表紙・グラビア・作品紹介・俳優紹介・読み物での扱いで分かるようにビリー・バーク主演の『グロリア物語』を大々的にフィーチャーしつつ、旧劇(連鎖劇)の市川海老十郎、女優として頭角を現しつつあった木下百合子の二人を複数誌面で扱い読者の関心を促しています。
先の例と同じで、表紙と目次どちらにも書かれていなくとも:
「総力特集:連続活劇界のニュータイプ『グロリア物語』検証」
「緊急特集:”ポスト取締規則”の時代へ。活動寫眞はどう変わるのか、現場からの声」
「小特集1:旧劇期待の新星・市川海老十郎」
「小特集2:木下百合子と日本活動花形女優誕生への道」
といった複数のテーマが扱われていることになるわけです。
国外の最先端の流れを消化しながらも、国内の映画製作にまつわる諸々の問題(検閲強化は妥当なのか。日本の活動界で女優の位置付けは向上されるべきではないのか)を反映させた雑誌作りができている。時代の潮流と同期をとりつつ批評意識は維持し続ける…そう考えていくと「通俗娯楽路線」の形容が必ずしも的確ではないと見えてきます。大衆受けと玄人受けはそもそも排他的な対立項ではありませんし、活動画報独自の形で両立させようとしていただけかと。この手の愛好家誌をゆめゆめ侮ることなかれ、自戒をこめてそうまとめておきます。
[出版者]
飛行社
[発行]
大正6年(1917年)10月1日
[定価]
三十二銭
[フォーマット]
菊判 21.8×15.2cm、220頁